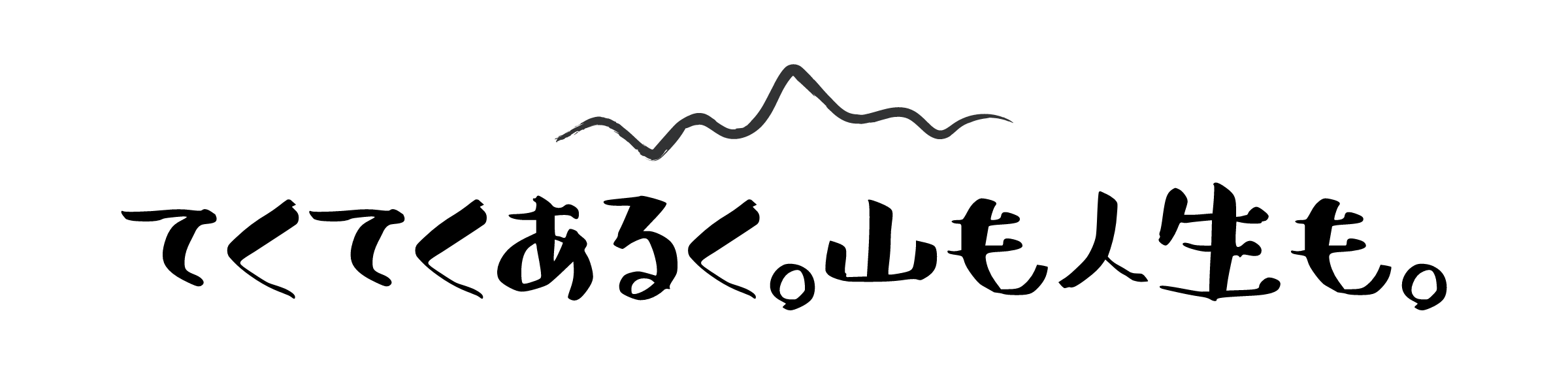夏の暑い日。鳥海山を登ったときに、とあるマダム2人に出会いました。
目次
鳥海山・鉾立登山口

鉾立登山口から出発する象潟口コースは鳥海山で一番登っているコースだけれど、この日はスタート直後からヘロヘロだった。
山トレーニングと題していつもの2倍の重量にしたザックの予想外の重さ。本領発揮した7月の猛暑。そして、寝坊して12時半からの遅いスタート……。出だしから心も体もダメダメで、登山開始たった5分でバテバテのヘロヘロ状態だった。
御浜小屋までは標準コースタイムで2時間ほど。ここまで行って引き返し17時までに下山完了するつもりだった。しかし、このペースだともっと手前で引き返さなくてはならないかもしれない。
そんな最中、2人のマダムに出会った。マダム2人も暑さにだいぶやられていて、私と同じようにバテバテのヘロヘロ状態だった。
2人は御浜小屋に泊まる予定だと言っている。それにしても遅いペースとやられ具合のため、御浜小屋すら無理じゃないか……と心配に。っていうか、自分だって歩いては止まる、を繰り返してたまに両膝に手ついて「あー」と唸るくらいだから人の心配してる場合じゃないんだけど。
「今日は本当に暑いわねぇ」
「曇ってるのになんでこんなに暑いのかしら」
「ぜんぜん足が動かない」
「ザックが重くて辛い」
なんて愚痴りながら(最後のセリフは私のただの言い訳)、3人で少しづつ前に進み続けた。
しかし、少し前を行くマダムの1人が登山道脇の木陰に座り込んでしまった。御浜小屋まで行けるかと余計心配に。いやまじで人の心配してる場合じゃないんだけどね。
しかしこの後、私の予想は見事に外れた。大丈夫だったのだ。
マダム2人が、「昔は北アルプスにしょっちゅう登るほど元気だったのにね〜」と話し始めた。その時の顔が、生気にあふれて生き生きしていたのだ。さっきまであんなにへばった顔してたのに。
「学生の頃から一緒に登り始めたのよね〜」
「お互い社会人になっても登ってて、でも結婚してからは疎遠になってたけどね」
「この歳になっても結局2人で登ってるんだもんね〜」
体はへばってても心がへばってない。とにかくすっごく楽しそうだった。
この時思った。このマダム2人は大丈夫だと。
「無理そうだったら引き返そうね」
2人はこう言いはじめていたけれど、たぶん引き返さないでゆっくり御浜小屋まで行くだろうな、と思った。
私は日帰りなのでそこまでゆっくりしてる余裕はない。ダメそうなら途中にある”賽の河原”というポイントで少し休んで引き返すことにする、とマダム2人に告げて先を急いだ。急いだっつっても、へばってるから全然スピードあがらないんだけど。
それでも、後ろに感じてたマダム2人の気配はすぐに消えた。登山道には私1人になった。
そして思った。
「なんか、いいな」
単独登山のジレンマ

私はほぼ単独登山だ。(友達がいないわけではないぞ!)
理由は簡単だ。自由気ままが好きな自己中野郎だからだ。コテコテの一人っ子B型である私は、何をするにも単独行動が基本。それは日常生活だけでなく山でも同じで、自由にペース配分をして、自由に写真をとって、自由に休んで、そうやって自分のペースで山と向き合いたいと思っている。
それなのに。仲間と楽しそうに登る人たちを羨ましいとも思う非常にめんどくさい人間である。
これは”単独登山のジレンマ”だ。”単独登山のジレンマ”は基本、山に登っていないときに顕著に現れる。SNSで楽しそうな投稿を見かけたとき。山岳雑誌で登山イベントのレポートを読んだとき。オフ会の情報を知ったとき……。そりゃあもう羨望の眼差しで指を加える。
しかし、山に入ってしまえばなぜかこのジレンマをあまり感じない。自分以外にも単独登山者はいるし、景色を見ながらゆっくり登っていれば人のどうのこうのなんて気にならないから。
にもかかわらずマダム2人に対してジレンマが発動した。2人の友情を「羨ましい」と思ったのだ。これは言い換えれば、いつもは下界に置いてくるはずの寂しさである。
「なんか、いいな」
私は山の上で、素敵な友情を微笑ましく思いながらも孤独を感じてしまったのだ。
賽の河原

標準コースタイムより大幅に遅れたけれど目標にしていた賽の河原に到着した。
この頃には雲の上にいた。日差しが直であたるようになって汗がどんどん吹き出してくる。しかし曇り空で暑いより青空が見えて暑いほうが気持ちはなぜか軽かった。空を見上げるたび、目に入るブルーが体力と気力を回復してくれた。
「私も御浜小屋までいけるかもしれない」
ここで少し休んで引き返そうと思った弱気な心が小さくなっていった。時間的には17時までの下山も問題なさそうだ。休憩もそこそこ、ザックを背負ったまま行動食のお菓子だけつまみ、私はすぐに御浜小屋までの登りにとりかかった。
途中、下山してくるおじいちゃんに「もう帰る時間だよ!」と大声をかけられた。御浜小屋で引き返すんで!と返すと、安心したような顔で「んだが、気をつけてなぁ」と言ってくれた。
足取りが軽い。水分をとりまくったことでザック容量が軽くなったってだけなのだろうけど、それにしても軽い。徐々に重さに慣れてきたのか、それとも青空の下を歩くのが楽しいからか。そこに吹く風が気持ちいいからか。とにかく私はいつもの調子をなんとか取り戻し、足を前に出し続けた。
前方に何かの撮影クルーがいた。かなりの大所帯だ。彼らの間を駆け上がるように登り、14時45分、御浜小屋に到着した。1人心の中でガッツポーズをした。
ふと、さっき出会ったマダム2人のことを思い出した。きっとマダムたちは山の上で何度も何度も2人でガッツポーズをしてきたに違いない。ずーっと。何年も。何十年も。
なんか、いいな。
御浜小屋

ザックを落とすように足元に下ろした。体に沈み込んでいた重力が一気に解放されて宙に浮いたかのような気分になる。急激に冷やされていく背中から山の風が入り込んで、かわりに疲労感が入れ替わるように放出されていった。
と同時に、足の裏に感じていた疲労感も放出されていく。ここまで歩いた実感も一緒に飛ばされていくようで少し寂し気もした。
大きな岩に座り、握ってきたおにぎりを頬張った(寝坊したくせに食料はちゃんとこしらえる)。頑張ったあとのおにぎりは普段の何倍も美味しい。一気に2つたいらげた。
あたりが急に賑やかになった。途中で追い越した撮影クルーが到着したようだ。彼らも御浜小屋に泊まるらしい。
撮影クルーの中のお兄さん2人と会話が弾んだ。1人は爽やかな好青年、もう1人はロン毛でいたるところにタトゥーが入っているオラオラ系だ。しかし2人とも山頂を見つめる目は少年のようにキラキラしていた。
今日は撮影で鳥海山にきたとのこと。いつもは2人で北アルプスに登っているらしく、おすすめの山やルートなどを教えてもらった。
日の傾きが色濃くなってきた。時刻は15時半。そろそろ下山しなければ。
「じゃあまた、どこかの山で」
「お互い気をつけて山を楽しもう」
お兄さんたちとお別れして、少し軽くなったザックを背負う。自分の汗で湿ったものを再度身につけるのは不快なはずだけれど、それすら山に吹く風がさらってくれる。しっかりとチェストハーネスを締めてきを引き締め、御浜小屋の前を通って登ってきた道を下りはじめた。
と、そのとき。ゆっくりだけれど確かな足取りで登ってくる2人の女性がいた。
「あっ!お姉さんだ〜!」
向こうのほうが早く気づいたようでこちらに手を降っている。私は駆け下りるようにして2人の元へ向かった。
「体調大丈夫だったんですね〜!よかった!」
「お姉さんも御浜までいけたんだね〜重い荷物背負って!よかったね〜!」
気づいたら、3人でガッツポーズをしていた。
「御浜小屋、今日は賑やかそうでしたよ」
「あら、それは楽しみね〜!」
「明日の山頂、気をつけていってきてくださいね!」
「お姉さんも気をつけて下山してね」
「じゃあ、またどこかの山で」
「そうねぇ!いつかまた、山でね」
私はマダム2人に背を向け一歩一歩山を下りた。2人の気配をそこらじゅうに感じながら。
下山

マダム2人と交流した時間はほんの少し。またどこかの山で、とは言ったものの、本当にどこかの山で会えるかどうかはわからない。私は今までどおり1人で山に登るし、マダム2人は2人で山に登り続けるんだと思う。
それでも。御浜小屋でのガッツポーズは、まぎれもない3人のガッツポーズだった。
”単独登山のジレンマ”は山に入ってしまえばあまり感じない、ではないのだ。山に入ってしまえば”みんなが仲間”なのだ。
マダム2人だけじゃない。登りの途中で心配してくれたおじいちゃん。御浜小屋で出会ったお兄さんたち。登山道ですれ違うときに「こんにちは」と挨拶した全ての人たち。みんないたじゃないか。ジレンマなんてただの自分の解釈であって、ありもしない勝手な思い込みだったんじゃないだろうか。
こんなことを思いながら無事に鉾立登山口に下山した。時刻は17時前。太陽がだいぶ傾いてあたり一面やんわりとオレンジっ気が増してきた。
車に戻り、着替えを済ませてから鉾立駐車場をあとにした。途中で寄ったコンビニでアイスを買い、頬張りながらスマホをいじる。SNSのタイムラインには、たくさんの人が仲間とワイワイと山を登っている様子が流れていった。
私は全てにいいねを押したあと、車のエンジンをかけて家路を急いだ。”単独登山のジレンマ”は、やっぱり山に登っていないときに現れるみたいだ。